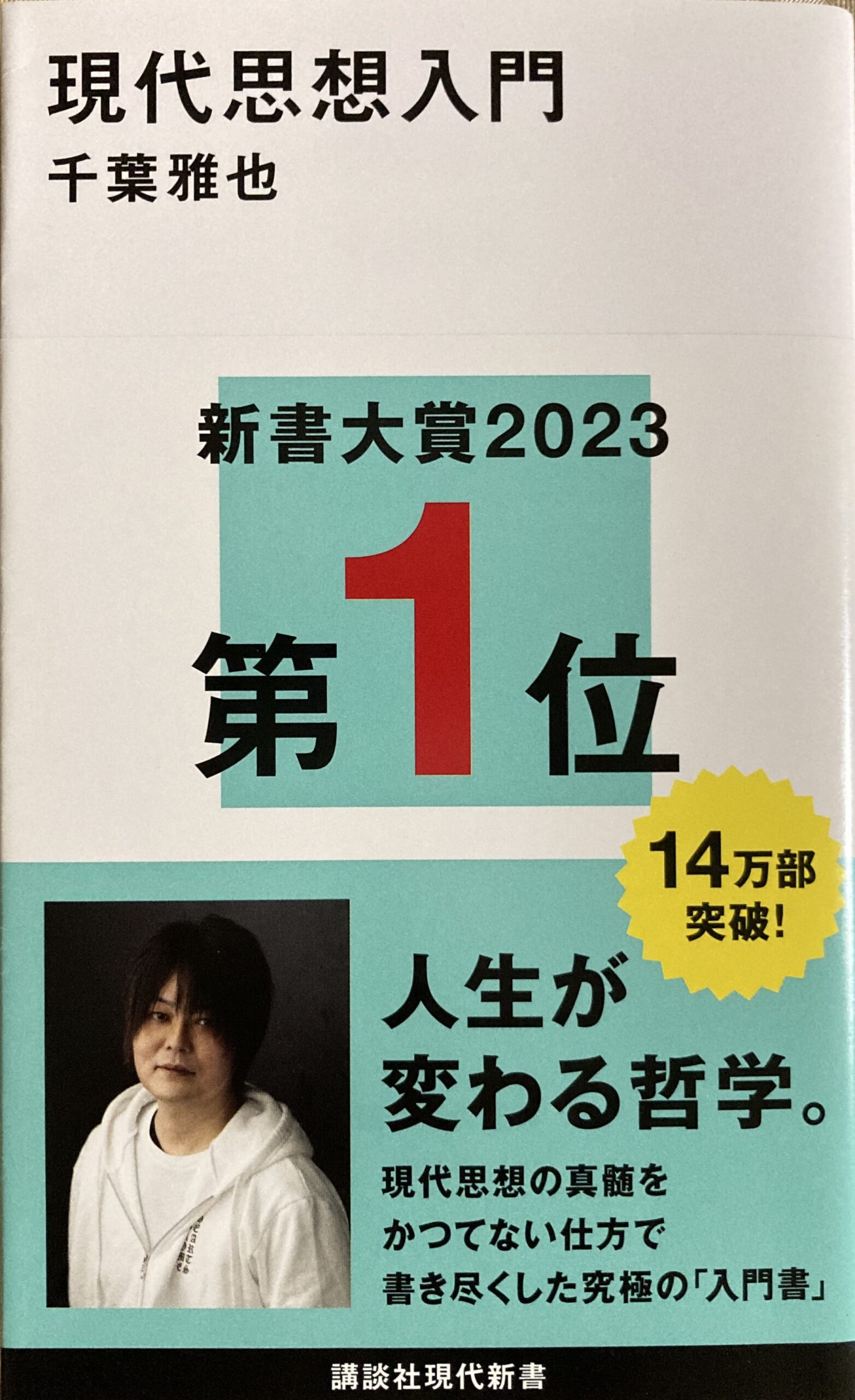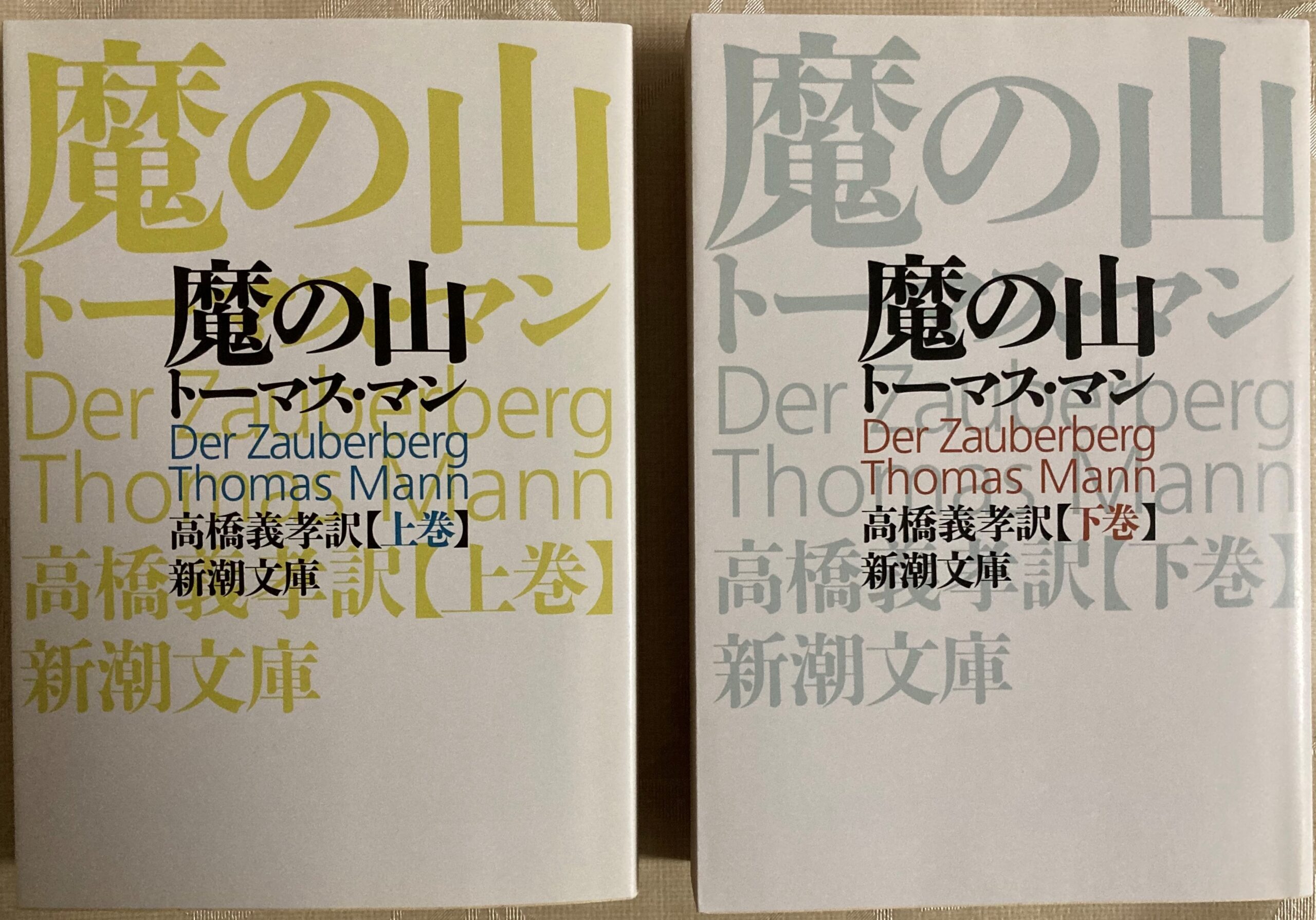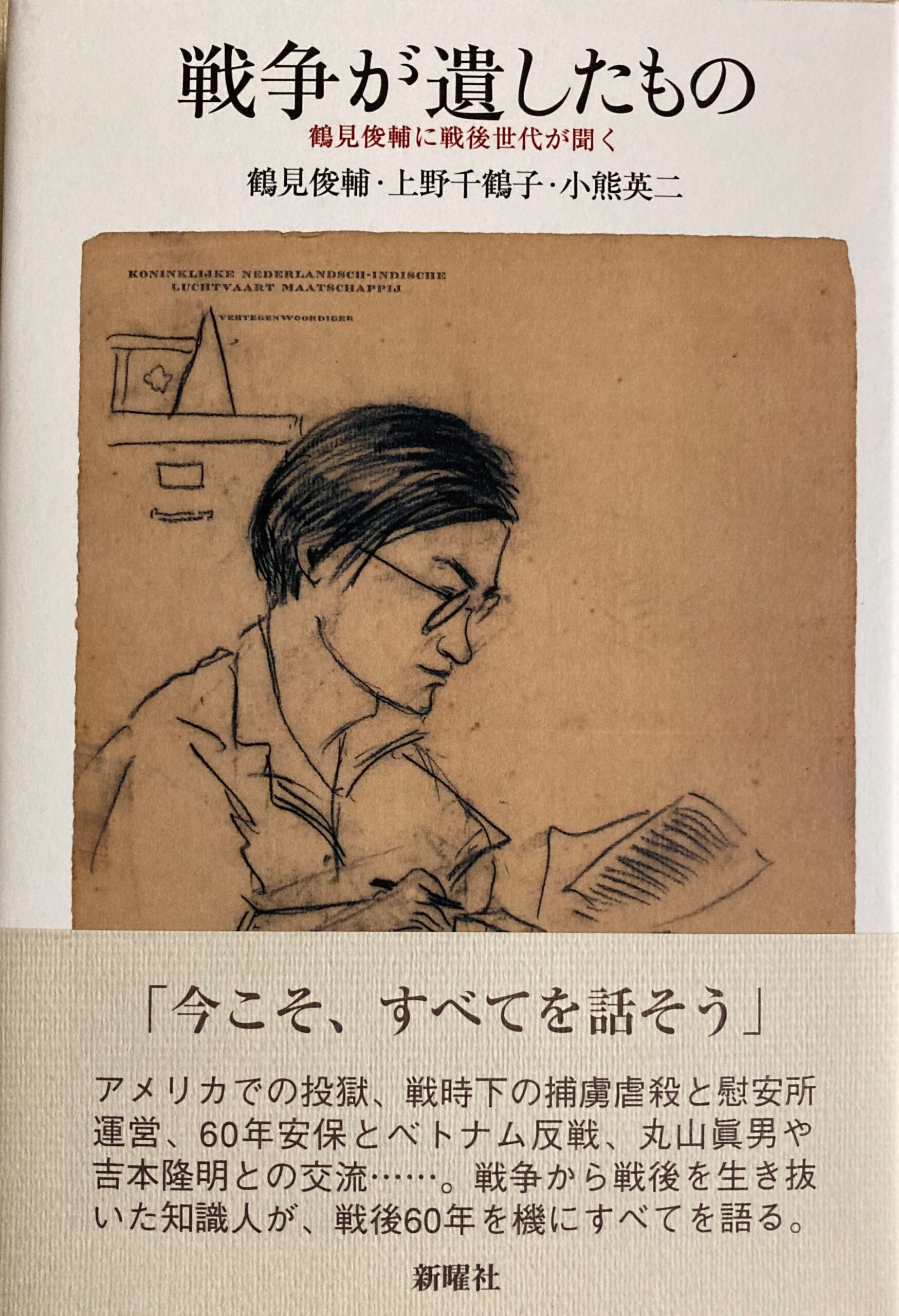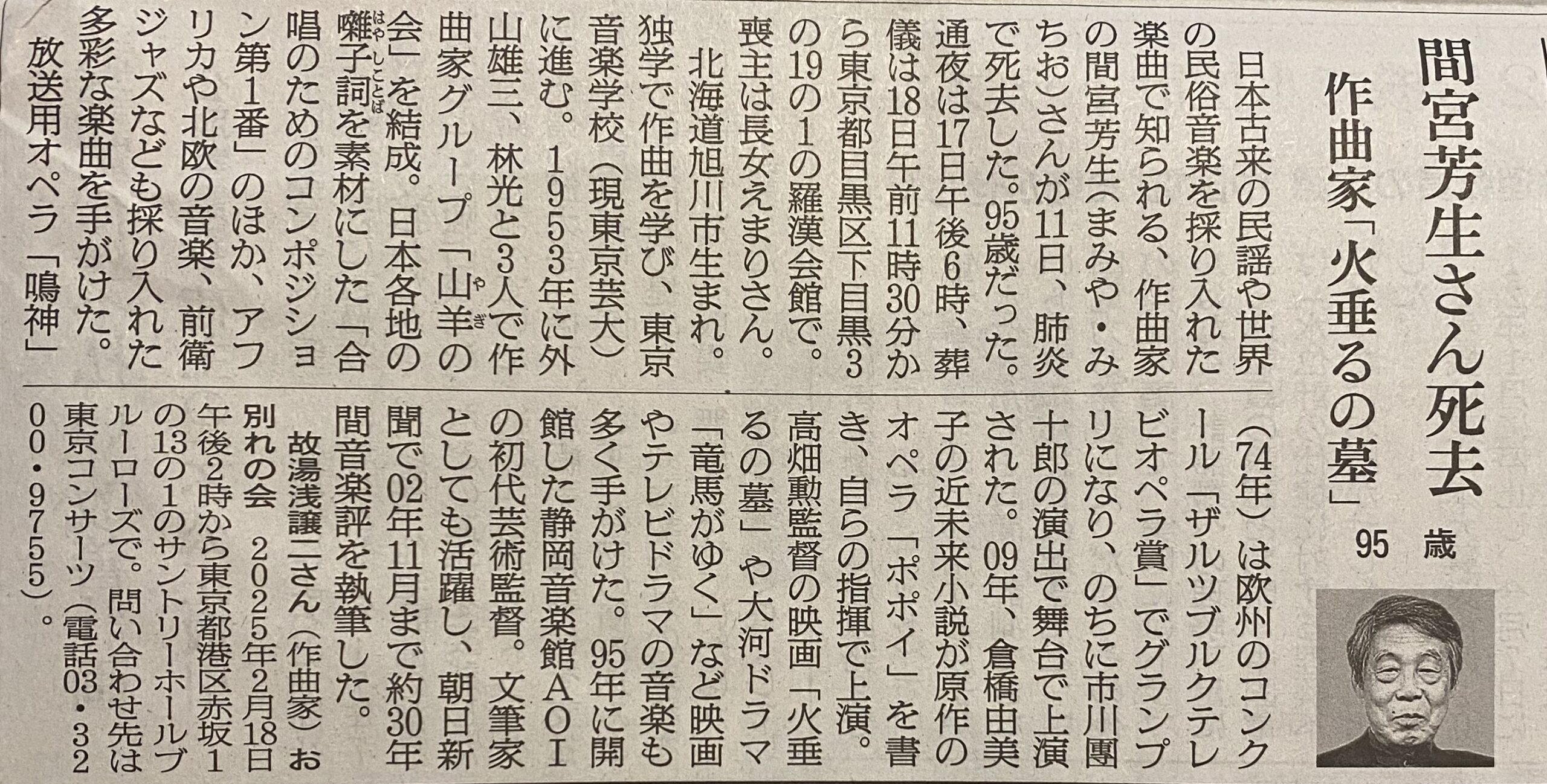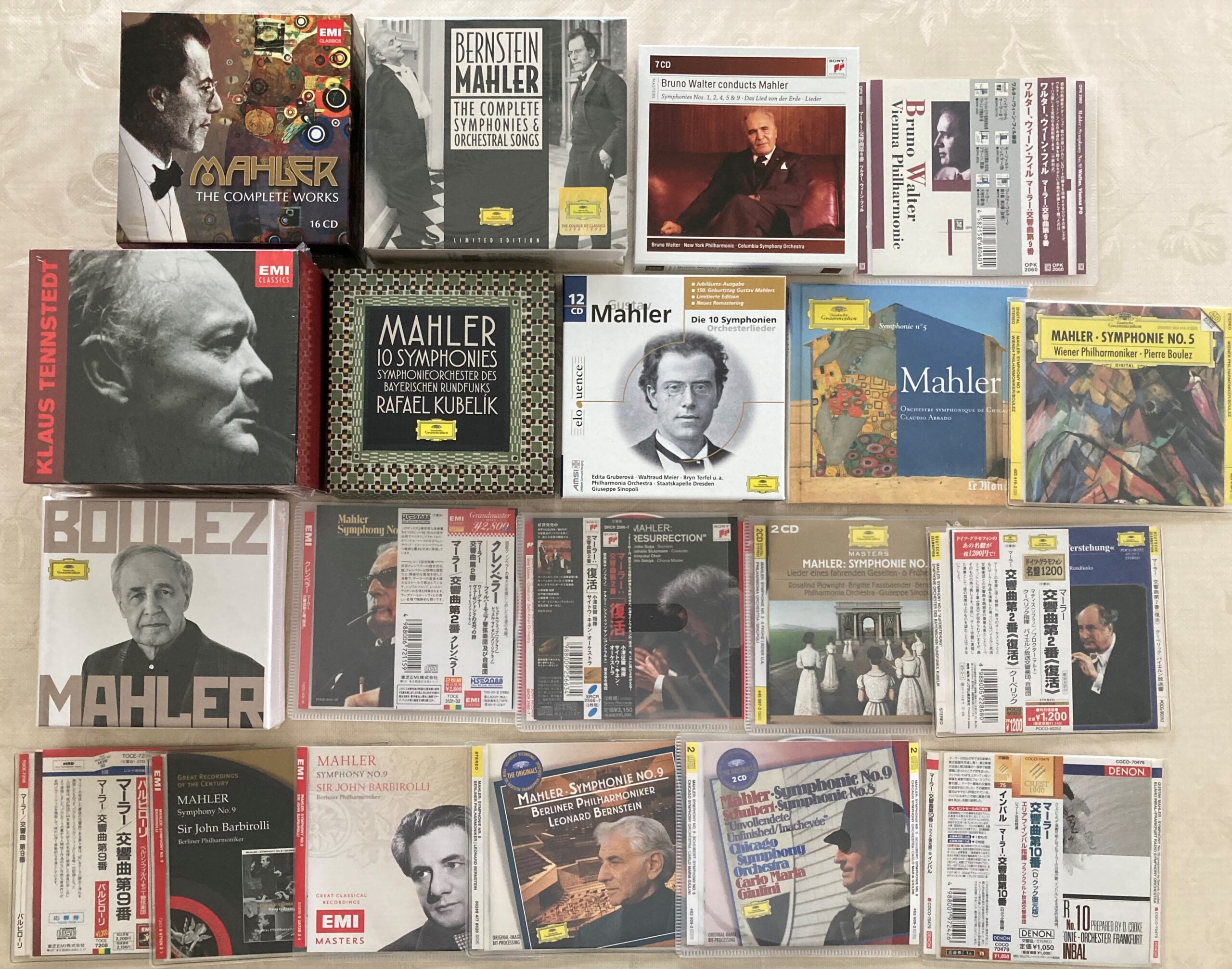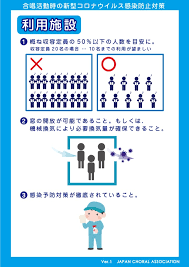目 次
再度、サザンカの剪定に取り組んだ
サザンカが咲き誇った後の剪定については、3月中旬にレポートした。サルスベリの遅い剪定に後、ついでの体で取り組んだものだった。
3月15日(土)のこと。その際に、左手の小指を切るというアクシデントを起こして、中々血が止まらずにと焦ったことは、このブログの熱心な読者には記憶に新しいところだと思う。
途中で指を切ってしまう怪我を負ったことで、この日の剪定は中途半端に終わってしまい、再度剪定しなければならないと結んだところだったが、急に思い立って、かなり早いタイミングで2度目の本格的な選定に取り組んだ。
そのレポートを簡単にさせてもらう。
スポンサーリンク
4月に入って2回に分けて実施
4月に入って早々の2日(水)と8日(火)の2回に分けて実施した。そういう意味では、この春先に通算3回の剪定を行ったことになる。
今回は2日(水)と8日(火)の2回の剪定を、合わせて報告する。
最終的なアフター写真は8日(火)の作業後のものを見てもらう。




スポンサーリンク
今回の剪定のポイントと目標
サザンカに限らず、樹木の剪定については、僕は全くのド素人で、何の知識も経験も持ち合わせていない。
見様見真似どころか、その見真似する人も実例も身近にないので、とにかく勝手に、ルール無視で闇雲に切るだけである。
できるだけ風通しを良くしてスッキリさせたいのだが、そのコツが全く分からず、適当に切っているだけだ。学校と言うか、教室のようなところに通って少し専門的なスキルを身に付けたいと思っているのだが、今のところそのチャンスもない。
そこで、今回は全部で17本植えてあるサザンカの、隣り合っているサザンカを一切接触しないように切ることを目標にした。隣同士のサザンカが互いに一切接触せずに離れている状態にすることにした。


根拠は何もない。そうやってとにかく木と木の間にスペースを設けて、少しでも風通しを良くして、スッキリさせたかっただけである。
そうやって一旦ルールを決め、目標を定めると、作業はかなり早く進んで、大いにはかどった。迷わずドンドン刈り込めた。これはいいアイデアだった。
結果、かなりスッキリしたと思う。
スポンサーリンク
裏のアパート側にお邪魔して伐採
もう一つは、我が家の側からの選定作業だけではどうしても効率性と生産性に欠け、結果として中途半端な剪定しかできないことが明確だったので、今回は燐家のアパート側の敷地内にお邪魔して、燐家との間を仕切っているフェンスからはみ出している枝や葉っぱを思い切ってバンバン剪定した。
フェンスから現にはみ出しているものだけではなく、今後、はみ出しそうな枝などもこの際、しっかりと切っておこうと、かなり刈り込んだ。
太い幹の一部がフェンスに接している部分もあって、それは剪定鋏みでは手に負えず、のこぎりで切ることもやった。

こうして燐家とのフェンスとの間もかなりスッキリした。しばらくはこれでいけると思う。




この2つの狙いで、今回はかなり思い切って剪定をすることができた。
見た目にもスッキリとして、「剪定したな」ということが、明確になったのではないかと思う。
これでアフター写真もそれらしいものが多少は用意するこことができた。
スポンサーリンク
アフター写真を見てほしい
今回は少しは剪定した効果を確認してもらえそうである。かなりスッキリしたことが分かってもらえるのではないか。
今回剪定のアフター写真を見てもらう前に、立派に花を咲かせてくれた直後のビフォーの状況を再度確認していただきたい。今年の年明け1月の写真である。




で、アフター写真だが、既に記事中に掲げたものもあるが、いくつか挙げるとこうなる。違いが分かってもらえるだろうか?




スポンサーリンク
これでシャクヤクに専念できる
かなり刈り込んだ感じは伝わってくるだろう。背の高さも少し短くしたのは分かるだろうか。
これだけ切ったように見えても、この時期のサザンカの勢いは凄まじいものがあって、新芽が凄い勢いでドンドン伸びてくる。しばらくするとまた、新しい葉っぱで覆われてくる。
植物の生命力を痛感させられる時期でもある。
こうしてしばらくはサザンカとはお別れ。半年後の10月後半以降から、蕾が付き始め、また寒い冬を彩ってくれることになる。
それまではしばしのお別れだ。その間に「チャドクガ」が付かないことだけには十分に注意したい。
これでシャクヤクに専念することができるようになった(笑)。
スポンサーリンク