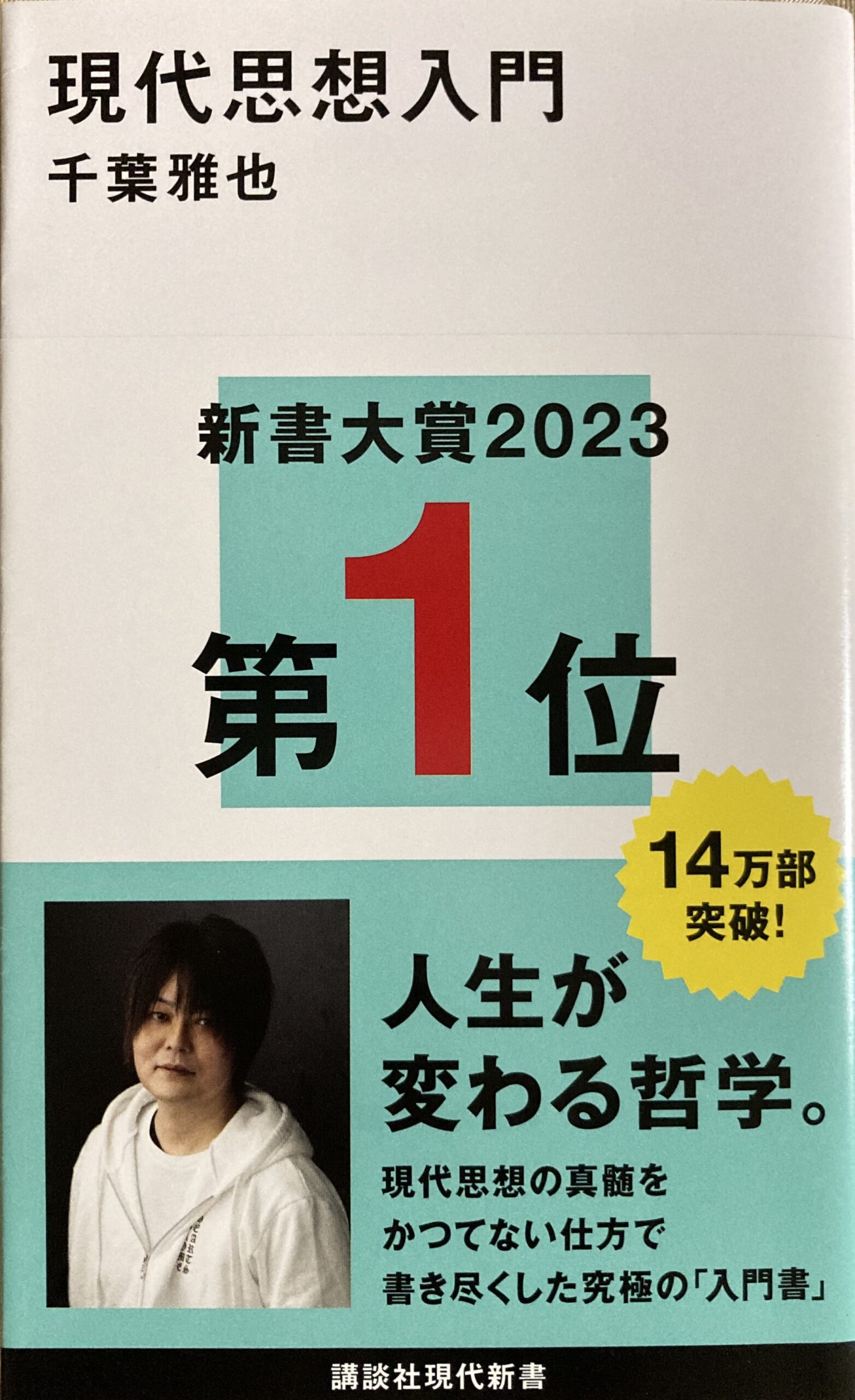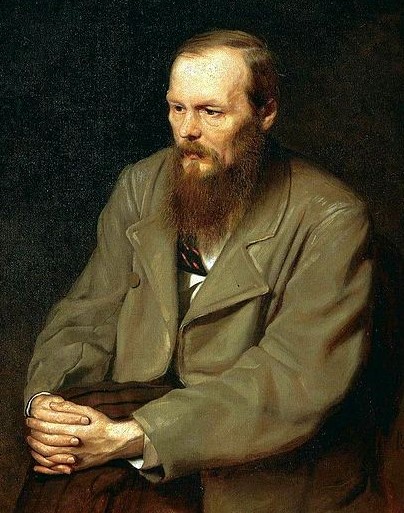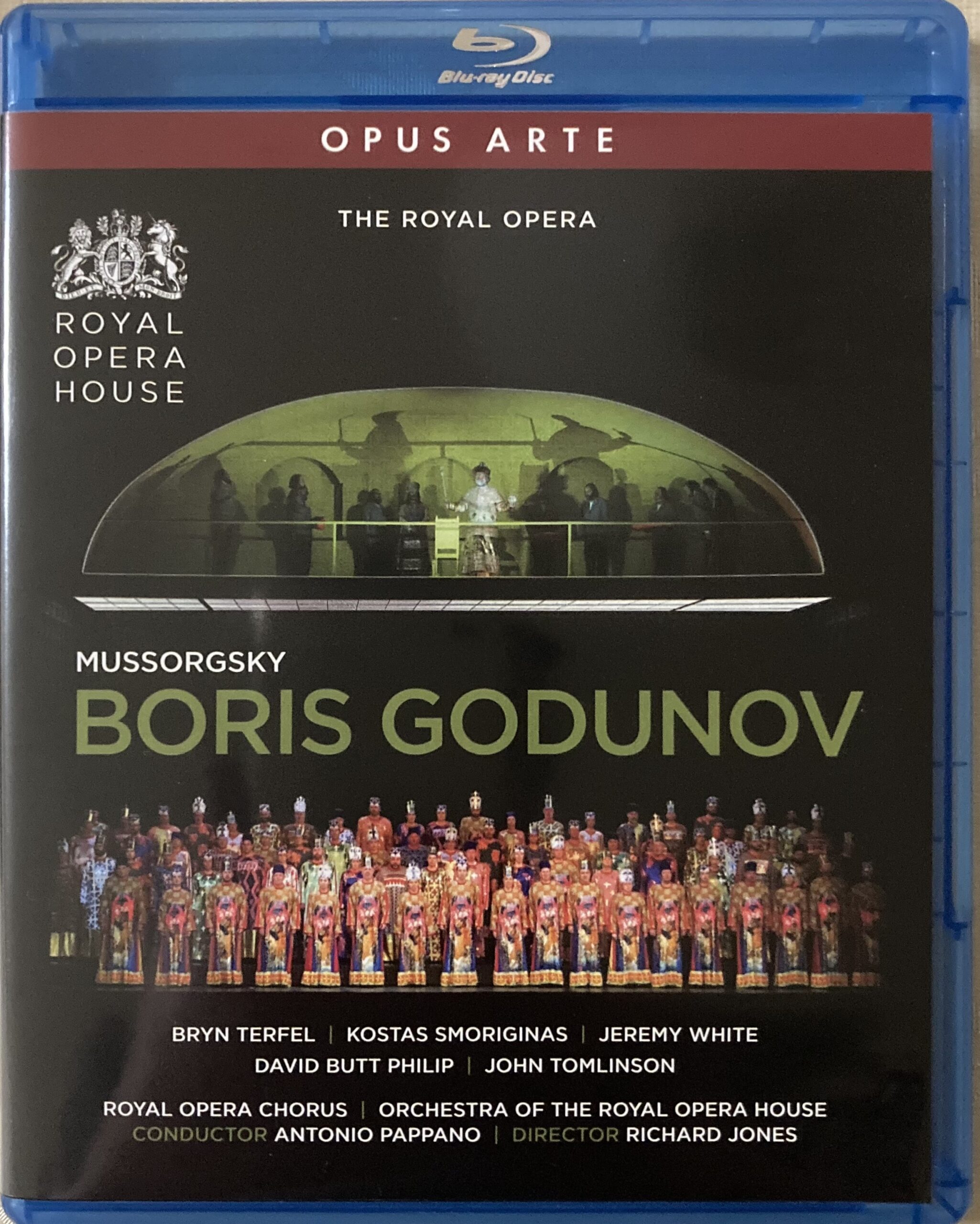目 次
「スリー・ビルボード」の感動が収まらない
これにはやられた。打ちのめされた。激しく心を揺さぶられ、感動が収まらない。
『スリー・ビルボード』がギンレイホールで上映されたのは、2018年の7月の後半だった。連日異常な暑さが続いていた頃だ。僕はこの映画を観るなり脳天に楔を打ち込まれたくらいに圧倒されて、一気にこの映画にのめり込んでしまった。ギンレイホールでは同一作品(2本立て)の上映は2週間サイクル。この間に僕は3回通い詰め、更に既に発売されていたブルーレイを即刻買い込んで、家族を巻き込んで繰り返し鑑賞。今日までに通算7回観たところである。そして観る度に新たな発見と感動があり、更にもっともっと繰り返し観たいとの欲求に駆られている。

ギンレイホールで観た映画では既に紹介してきた『タレンタイム』や『淵に立つ』など生涯忘れえぬ名作や問題作に出会わせてもらったが、この『スリー・ビルボード』ほど心を揺さぶられた映画はない。近年稀にみる真の傑作だと断言したい。
スポンサーリンク
ストーリーは
ストーリーもユニークなものだ。アメリカ南部のミズーリ州。とある田舎の母親が突然、さびれた道路脇に真っ赤な巨大な3枚の広告板を掲げるところから始まる。その広告には、地元警察への痛烈な批判が書かれていた。この母親の娘が9ヵ月前に極めて残忍な方法で襲われ、殺害されたのに、地元警察は真剣に捜査を進めず、放置されており、母親が地元の警察署長を名指しで批判した広告板だったのだ。批判された警察署長は住民の人望が厚く、加えてがん療養中で余命が長くないことが知れ渡っていただけに、彼女のやり方に批判が殺到。特に怒りが収まらなかったのは所長を実の父親のように慕う黒人を徹底的に嫌っている差別主義者の暴力警官だった。
ところが母親もさる者で、住民の批判や警察官の圧力など全く気にも留めず、全面衝突にも発展しそうな一触即発状態に。3枚の巨大な広告板を巡って繰り広げられる想像を絶する人間模様と、劇的にして予測不可能な展開に一瞬たりとも目が離せなくなる。そもそも娘を虐殺した犯人は捕まるのだろうか。

一体どんな映画なんだ?!
一体これは何という映画だろう。人間の本質をどこまでも掘り下げた稀有な映画と言うしかない。人間描写が生半可じゃないのだ。ここまで人間の本質と性(さが)を掘り下げた映画も稀だ。登場人物が全員、一筋縄ではいかない一癖も二癖もある人間ばかり。その上、登場人物の心のありようが微妙に変化し、変容を来していくので、深みはドンドン深遠さを増すことになり、観ている方は本当にこのドラマの奥深さ、人間観察眼の尋常じゃない深みに驚きを禁じ得なくなる。![]()
俳優のこと
主役の母親役を演じるのはフランシス・マクドーマンド。知る人ぞ知る名女優。あの有名なコーエン兄弟(映画監督・脚本家・映画プロデューサー)の「ファーゴ」でアカデミー主演女優賞を獲得し、今回この映画で二度目の主演女優賞を獲得。美人とは程遠く、男以上に粗野で暴力的なウルトラおばさんを演じ切る。その存在感と抜群の演技力が周囲を圧倒してしまう。
ちなみにこのフランシス・マクドーマンドは、コーエン兄弟の兄であるジョエル・コーエンと結婚している。もう40年近くも円満な家庭を築いていることは知っておいてもらいたい。
批判される警察署長役のウディ・ハレルソンもさすがに素晴らしいが、彼を慕う暴力警官役のサム・ロックエルがすごい。これでアカデミー賞助演男優賞を獲得したが、本当にこれは必見の演技。
監督と脚本のマーティン・マクドナーに脱帽
そしてやはり唸ってしまうのは、監督と脚本のマーティン・マクドナーだ。私はこの人を知らなかったが、ものすごい力量と手腕で、これから世界の映画シーンをリードするとんでもない逸材だと信じて疑わない。もともとイギリスの演劇界では著名な人で、自ら戯曲を書き、演出もする演劇界の天才らしい。それでここまでのシナリオが描けたんだと納得。それほどこの映画の中で語られる「会話」は奥が深い。登場人物たちが発するほんの短い一言、一言に生命が宿り、心の琴線を刺激してやまない。こんな体験は滅多にできるものではない。

スポンサーリンク
驚嘆すべき撮影技術が出てくるが
映像上のテクニックもものすごいものがあり、シネフィルを狂喜させる。ここにはとんでもないワンシーンワンカット(長回し)が出てくる。これは驚嘆すべきものでどうやって撮影したのか想像もできないものだ。その他、映像と音楽のギャップを多用するなど驚異的なテクニックが目白押し。
でもそんなことはどうでもいいというくらいに、内容そのものが素晴らしい。こんなに対立し、いがみ合う人間模様ばかり描かれるのに、とどのつまりは愛。最後は愛に尽きてしまう。そして一見救いのないやり切れない映画のようでいて、愛はどこまでも深く、救いの光は見えそうだ。
映画の登場人物たち以上に、この映画を観る者も心の変容を迫られることになる。
ちなみにこの年のキネマ旬報ベストテンではぶっちぎりのベストワン。読者選出ベストテンでも断トツのベストワンで二冠達成。当然の結果だろう。
近年稀にみる真の傑作だと断言したい。音楽がまた最高で、これを観逃したら、大変なことになる。
![]()